- エドワード懺悔王(ざんげおう)は、11世紀(在位1042年~1066年)のイングランド国王。ノルマン人による征服(ノルマン・コンクエスト)直前の、アングロ・サクソン王朝(ウェセックス家)最後の王の一人です。
- 1043年の今日、4月3日に、彼はウィンチェスター大聖堂でイングランド国王として戴冠しました。
- 非常に敬虔なキリスト教徒として知られ、ロンドンのウェストミンスター寺院の建設に情熱を注いだことが最大の功績とされています。その信仰心から、死後、カトリック教会によって聖人(聖エドワード懺悔王)と認められました。
- しかし、彼には世継ぎがおらず、その死後にイングランドの王位継承をめぐる争いが勃発。これが、ノルマンディー公ウィリアムによるイングランド征服(ノルマン・コンクエスト、1066年)という、イングランド史の大きな転換点を引き起こす直接的な原因となりました。
4月3日。今から約1000年もの昔、1043年のこの日、イングランドの歴史において重要な意味を持つ一人の王が、その頭上に王冠を戴きました。彼の名はエドワード。後世、「懺悔王(ざんげおう、the Confessor)」という特別な称号で呼ばれ、さらにはカトリック教会の聖人にまで列せられた、非常に敬虔な国王です。
しかし、その敬虔さとは裏腹に、彼の治世と、特にその後継者問題は、イングランドを大きな動乱へと導くことになります。今回は、聖エドワード懺悔王の波乱に満ちた生涯と、彼が歴史に残した足跡、そして今日4月3日という戴冠記念日にちなんで、その物語を紐解いていきましょう。
亡命王子からイングランド国王へ
エドワード(Edward)が生まれたのは、11世紀初頭(1003年か1005年頃)。父はアングロ・サクソン系のイングランド王エゼルレッド無策王、母は海峡の向こう、フランスのノルマンディー公国の公女エマという、由緒ある血筋でした。しかし、当時のイングランドは、デンマークから来たヴァイキング(デーン人)の侵攻に絶えず脅かされており、エドワードの幼少期は安穏とはほど遠いものでした。
デーン人の勢力が増し、ついにはクヌート(カヌート)大王がイングランド王位を奪うと、若きエドワードは母エマと共に、母の故郷であるノルマンディー公国への亡命を余儀なくされます。彼はそこで、実に約25年間という長い年月を過ごすことになりました。この亡命生活は、彼の深いキリスト教信仰を育み、またノルマンディーの文化や人々への親近感を形成する上で、決定的な影響を与えたと言われています。
転機が訪れたのは1042年。イングランドを治めていたデーン系の王(クヌート大王と母エマの間に生まれた異父弟ハーデクヌーズ)が、世継ぎのないまま急死します。イングランド国内ではデーン人支配への反発も高まっており、亡命先のノルマンディーにいたエドワードに白羽の矢が立ちました。イングランド国内で最も強大な力を持つ貴族、ウェセックス伯ゴドウィンらの支持を得て、エドワードはついに故国へ帰り、正統なアングロ・サクソン王朝(ウェセックス家)の王として即位することになったのです。
戴冠、そして波乱の治世(1043年4月3日)
そして、1043年の今日、4月3日。エドワードは、当時のイングランドの首都の一つであったウィンチェスターの大聖堂で、盛大な戴冠式を執り行いました。長年の亡命生活を乗り越え、彼が父祖伝来のイングランド国王となった瞬間でした。
エドワード王の治世(1042年~1066年)は、大きな外敵の侵攻もなく、比較的平和な時代であったと評価されています。しかし、国内に目を向けると、常に権力闘争の緊張が漂っていました。その中心にいたのが、エドワードの即位を後押ししたウェセックス伯ゴドウィンとその一族(後のイングランド王ハロルド2世の父であり、エドワードの義父にもなる)です。
エドワードは、長年の亡命生活の影響からか、宮廷や教会組織の要職に、ノルマンディー時代からの旧知であるノルマン人を重用する傾向がありました。これは、イングランド土着のアングロ・サクソン系の有力貴族たち、とりわけ強大な勢力を誇るゴドウィン一族にとっては面白くありません。両者の対立は次第に深まり、1051年にはエドワードがゴドウィン一族を一時的にイングランドから追放するという事態にまで発展します。しかし、翌年、ゴドウィン一族は武力を背景に帰国・復権を果たし、これ以降、エドワードの宮廷はゴドウィン家の強い影響下に置かれることになります。
敬虔なる信仰心:ウェストミンスター寺院の建設
政治の舞台では有力貴族との駆け引きに苦労したエドワードですが、彼は個人的には非常に敬虔なキリスト教徒であり、その信仰深さは後世まで語り継がれることになります。
彼の信仰心の最も偉大な、そして今日まで形として残る証しが、ロンドンにあるウェストミンスター寺院(Westminster Abbey)の建設です。彼は、ノルマンディーで見た壮大なロマネスク様式の教会建築に深い感銘を受け、イングランドにもそれに匹敵する神の家を建てることを熱望しました。私財を惜しみなく投じ、長い年月をかけて、テムズ川のほとりに壮麗な教会堂(当時はベネディクト派の修道院付属教会)を建立したのです。この教会は、エドワードの死のわずか数日前、1065年の暮れに献堂式が行われました。そして、この場所は以後、歴代イングランド(そしてイギリス)国王の戴冠式が行われ、多くの王族や偉人が眠る、国家にとって最も神聖で重要な場所の一つとなったのです。
後継者問題とノルマン・コンクエストへの道
エドワード懺悔王は、イングランドに平和と信仰をもたらそうと努めましたが、彼の治世には一つ、決定的な問題がありました。それは、王位を継ぐべき子供がいなかったことです。彼はウェセックス伯ゴドウィンの娘イーディスを王妃に迎えましたが、二人の間にはついに世継ぎが生まれませんでした。(その理由については、「王が敬虔すぎるあまり夫婦の営みを断っていた」という中世の伝説から、「王妃との政治的な関係が悪かったため」、「医学的な不妊」など、様々な説があります。)
この後継者の不在は、エドワードの晩年から、彼の死後にかけて、イングランドの将来に暗雲をもたらすことになります。誰が次の王となるのか? 主な候補者は3人いました。
- ハロルド・ゴドウィンソン
ウェセックス伯ゴドウィンの息子で、イングランド国内で最も有力な貴族。エドワード王の義理の兄弟でもある。 - ノルマンディー公ウィリアム
エドワード王の母エマの甥にあたる、フランスの有力諸侯。エドワード自身が生前にウィリアムに王位を約束した、とウィリアムは主張。 - ノルウェー王ハーラル3世(苛烈王)
かつてイングランドを支配したデーン人の王クヌートの血縁関係を主張し、王位を狙う北欧の猛将。
1066年1月5日、エドワード懺悔王は静かに息を引き取り、自らが愛したウェストミンスター寺院に埋葬されました。言い伝えによれば、王は死の床でハロルド・ゴドウィンソンを後継者に指名したとされています。イングランドの賢人会議(ウィテナゲモート)はこれを受け、ハロルドをイングランド王ハロルド2世として即位させました。
しかし、これを認めないノルマンディー公ウィリアムとノルウェー王ハーラル3世は、それぞれ大軍を率いてイングランドに攻め込んできます。ハロルド2世は、まず北から侵攻してきたノルウェー軍をスタンフォード・ブリッジの戦いで見事に撃退しますが、息つく間もなく南岸に上陸したウィリアムのノルマン軍と対峙しなければなりませんでした。そして、1066年10月14日、イングランドの運命を決するヘイスティングズの戦いで、ハロルド2世は奮戦むなしく戦死。イングランド軍は敗北します。
この勝利によって、ノルマンディー公ウィリアムはイングランド王ウィリアム1世(後に「征服王(the Conqueror)」と呼ばれる)となり、イングランドはノルマン人による支配の時代、すなわち「ノルマン・コンクエスト」を迎えることになりました。アングロ・サクソン人の王朝は終わりを告げ、イングランドの言語、文化、社会構造は、これ以降大きく変貌していくことになるのです。エドワード懺悔王の死と、彼が生前に解決できなかった後継者問題が、この歴史的な大転換の直接的な引き金となったのでした。
聖王としての遺産:懺悔王と列聖
エドワード懺悔王は、政治家としては必ずしも強いリーダーシップを発揮できたわけではありませんでしたが、その深い信仰心、平和を愛する人柄、そして貧しい人々への慈悲深さは、彼の死後、ますます人々の間で語り継がれるようになりました。彼の墓を訪れると病気が治る、といった奇跡の噂も広まり、次第に聖人として崇敬されるようになります。
そして、彼の死から約100年後の1161年、ローマ教皇アレクサンデル3世は、エドワードを正式に聖人として認め(列聖)、「懺悔王(Confessor)」の称号を追贈しました。「懺悔王」とは、キリスト教の信仰を守るために殉教したわけではないけれども、その生涯を通じて篤(あつ)い信仰を貫き、模範的な生涯を送った聖人に与えられる特別な称号です。
聖エドワード懺悔王は、その後長くイングランドの守護聖人の一人として国民から敬愛され、彼が情熱を傾けて再建したウェストミンスター寺院は、今日に至るまでイギリス王室と国家にとってかけがえのない精神的な支柱であり続けています。
まとめ:歴史の転換点に生きた敬虔な王
1043年の今日、4月3日に戴冠したエドワード懺悔王。彼の生涯は、アングロ・サクソン王朝の黄昏と、ノルマン王朝の黎明という、イングランド史の大きな転換点に位置しています。
国内の権力闘争に苦慮し、結果的に国を大きな動乱へと導く後継者問題を残してしまいましたが、その一方で、深い信仰心に生きた証として、ウェストミンスター寺院という壮大な建築物を後世に残しました。政治的な評価は様々ですが、「聖王」として人々に記憶され続けるエドワード懺悔王。彼の戴冠記念日である今日、中世イングランドの歴史に思いを馳せてみるのはいかがでしょうか。
※本記事では英語版も参考にしました











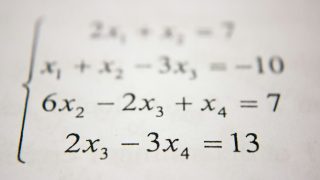











コメント