- アルド・モーロ(1916年~1978年)は、第二次世界大戦後のイタリアを代表する重鎮政治家。キリスト教民主主義のリーダーとして、首相を5回務めました。
- 彼は、冷戦下で対立していたキリスト教民主主義とイタリア共産党が協力し合う「歴史的妥協」という大胆な政策を進めようとしていました。
- しかし、その歴史的妥協に基づく新内閣が発足するまさにその日、1978年3月16日、彼は極左テロ組織「赤い旅団」によってローマで誘拐され、一緒にいた護衛5名は殺害されました。
- 赤い旅団はモーロを人質にとり、収監中の仲間の釈放を要求しましたが、イタリア政府は「テロに屈しない」として交渉を拒否。モーロは約55日間監禁された末に殺害されました。
- そして1978年の今日、5月9日、彼の遺体がローマ市内の車のトランクから発見されました。この事件はイタリア社会に計り知れない衝撃を与え、「鉛の時代」と呼ばれるテロと暴力の時代の最も悲劇的な出来事として記憶されています。
今から47年前の今日、1978年5月9日。イタリアの首都ローマの路上で、一台の乗用車のトランクから、衝撃的なものが見つかりました。それは、約2ヶ月もの間、行方不明となっていたイタリア政界の最重要人物、アルド・モーロ元首相の、変わり果てた姿でした。
彼は、当時イタリアを恐怖に陥れていた極左テロ組織「赤い旅団(Brigate Rosse)」によって誘拐され、そして無情にも殺害されたのです。イタリアの戦後史において最も影響力のある政治家の一人であったモーロの誘拐と死は、イタリア国民に計り知れない衝撃と悲しみを与え、国の政治を大きく揺るがしました。
なぜ彼はテロリストの標的となり、そしてなぜ救出されることなく、悲劇的な最期を遂げなければならなかったのでしょうか? イタリアが「鉛の時代(Anni di piombo)」と呼ばれた、テロと暴力が吹き荒れた時代の闇を象徴するこの事件について、その背景と経緯を振り返ります。
アルド・モーロとは? 戦後イタリアの重鎮政治家

アルド・モーロ(Aldo Moro)は、1916年に南イタリアのプーリア州で生まれました。大学では法律を学び、法学者・教授としての道を歩み始めますが、第二次世界大戦後、イタリアが王政から共和制へと移行する中で、本格的に政治の世界へと足を踏み入れます。
彼は、戦後のイタリア政治において、長期間にわたり政権与党の地位を占めることになる中道右派(または中道)の政党「キリスト教民主主義」に参加し、すぐにその穏健で誠実な人柄と、卓越した調整能力、そして深い知性によって頭角を現しました。
彼は、非常に複雑で分裂しがちだったイタリア政界において、異なる意見を持つ人々や政党の間を取り持ち、合意を形成する能力に長けていました。その手腕を買われ、イタリア共和国の首相の座に、断続的ながら合計5回も就任しました(1963年~1968年の間に3回、1974年~1976年の間に2回)。これはイタリアの戦後史において、ジュリオ・アンドレオッティに次ぐ多さです。首相以外にも、外務大臣、法務大臣、教育大臣など、数々の重要な閣僚ポストを歴任しました。
そして、彼が誘拐された1978年当時は、キリスト教民主主義の党首(書記長)という、党のトップの地位にあり、イタリア政界において絶大な影響力を持つ、まさに国家の重鎮と呼ぶべき存在でした。
「歴史的妥協」:冷戦下のイタリアでの大胆な試み
アルド・モーロが、その政治生命をかけて取り組もうとしていたのが、「歴史的妥協」と呼ばれる、非常に大胆な政治構想でした。
当時のイタリアは、アメリカを中心とする西側陣営と、ソビエト連邦を中心とする東側陣営が対峙する「冷戦」の最前線の一つでした。イタリア自身は西側陣営(NATO加盟国)に属していましたが、国内には西ヨーロッパで最大規模を誇る強力なイタリア共産党(PCI)が存在し、常に高い得票率を得て、政権獲得の機会をうかがっていました。
一方、与党であるキリスト教民主主義は、第一党ではあり続けたものの、単独で安定した政権を運営することは難しく、他の小政党との連立に依存する、不安定な政権運営が続いていました。
さらに、1970年代のイタリアは、「鉛の時代(Anni di piombo)」と呼ばれる、極めて困難な時期にありました。極左過激派(「赤い旅団」はその代表格でした)による誘拐、爆弾テロ、殺人といった暴力行為と、それに対抗する極右ネオファシストによるテロや破壊活動が、イタリア全土で頻発し、社会は深い不安と混乱に覆われていました。経済も停滞し、労働争議も激化していました。
このような危機的な状況を乗り越えるために、アルド・モーロは、従来のイタリア政治のタブーとも言える、画期的なアイデアを提唱し始めます。それは、国の安定と改革のためには、長年対立してきた与党・キリスト教民主主義と、野党第一党である共産党が、イデオロギーの違いを超えて協力し合うべきだ、という考えでした。これが「歴史的妥協」です。
モーロは、共産党を完全に敵視し、政権から排除し続けるのではなく、彼らの協力を得ることで、より幅広い国民的合意に基づいた安定政権を樹立し、テロとの戦いや、経済・社会改革といった、イタリアが直面する困難な課題に、国を挙げて取り組むべきだと考えたのです。
この構想は、キリスト教民主主義党内の保守派や右派、そして共産主義を脅威とみなすアメリカなどからは、強い警戒感と反発を受けました。しかし、モーロは持ち前の粘り強さで党内や関係各方面への説得を続けました。一方、イタリア共産党側(当時の書記長はエンリコ・ベルリンゲル)も、ソ連との一定の距離を保ち、西欧型の議会制民主主義の枠内での活動を目指す「ユーロコミュニズム」路線をとっており、政権への影響力を合法的に拡大する機会として、この「歴史的妥協」に前向きな姿勢を示し始めていました。
そして、ついに1978年春、共産党が閣外からではあるものの、キリスト教民主主義が主導する新しい政権(ジュリオ・アンドレオッティ首相)を信任し、政策に協力するという、歴史的な合意が形成されようとしていたのです。
運命の日:白昼の誘拐劇 (1978年3月16日)
しかし、このイタリア政治における歴史的な転換点が訪れようとしていた、まさにその日に、悲劇は起こりました。
1978年3月16日の朝。この日は、アンドレオッティ新内閣がイタリア議会で信任投票を受ける、重要な日でした。「歴史的妥協」の実現に心血を注いできたアルド・モーロは、キリスト教民主主義党首として、この信任投票に臨むため、自宅から車で議事堂へと向かっていました。
午前9時過ぎ、ローマ市内の閑静な住宅街にあるファニ通りを走行中、モーロが乗ったフィアット130と、彼を警護するアルフェッタの2台の車列が、待ち伏せていたテロリスト集団によって襲撃されました。犯人たちは、盗難車で進路を塞ぎ、航空会社の制服を偽装するなど、周到に計画を練っていました。そして、自動小銃などをためらうことなく乱射し、モーロの車を守っていた5人の警護官(警察官2名、国家憲兵3名)全員を、その場で射殺するという凶悪さを見せつけました。
そして、アルド・モーロ自身は、傷一つなく、そのまま拉致され、別の車に乗せられて現場から連れ去られてしまったのです。白昼のローマで起こったこの大胆不敵な犯行は、イタリア全土を震撼させました。
まもなく、犯行声明が出されます。犯人は、当時イタリアで最も活動的で、最も恐れられていた極左テロ組織「赤い旅団(Brigate Rosse)」でした。彼らは、マルクス・レーニン主義の思想に基づき、武装闘争によるイタリア国家の転覆と、プロレタリアート(労働者階級)による革命を目指す過激派グループでした。彼らはそれまでにも、企業経営者や政治家、裁判官などを標的とした誘拐、傷害(「脚撃ち」と呼ばれた)、そして殺人事件を繰り返していました。
赤い旅団にとって、キリスト教民主主義という「資本主義国家体制」の中心に長年いた指導者であり、さらに彼らが「裏切り者」と見なす共産党との連携(歴史的妥協)を進めようとしていたアルド・モーロは、まさに「国家の心臓部」を象徴する存在であり、彼を誘拐・打倒することは、彼らの革命闘争における最大の戦果となると考えたのです。
55日間の監禁、そして政府の「非情」な選択

アルド・モーロの誘拐は、イタリア社会に計り知れないほどの衝撃と恐怖を与えました。政府は直ちに非常事態を宣言し、警察と軍を総動員して、文字通りローラー作戦のような大規模な捜索と、赤い旅団メンバーの追跡を開始しました。しかし、赤い旅団は巧みに潜伏し、捜査当局はモーロがどこに監禁されているのか、その手がかりを掴むことができませんでした。
赤い旅団は、誘拐したモーロを「人民の法廷にかける」と宣言し、彼の解放と引き換えに、イタリアの刑務所に収監されている自分たちの仲間であるテロリスト十数名を釈放することを、イタリア政府に対して要求しました。
監禁されたモーロは、約55日間という長い間、赤い旅団のアジト(場所は不明)に閉じ込められました。この極限状態の中で、彼は多数の手紙を書いたとされています。(これらの手紙は、赤い旅団によって検閲・公開されたものもあり、本当にモーロ本人の自由な意志だけで書かれたものなのか、あるいはテロリストによる強要や代筆があったのではないか、という点については、後に多くの議論や分析が行われました。)
これらの手紙の中で、モーロは家族や友人、キリスト教民主主義の党幹部、そして個人的にも親交のあった当時のローマ教皇パウロ6世などに向けて、自らの苦境を訴え、そして何よりも自身の命を救うために、政府が赤い旅団との交渉に応じ、囚人交換の要求を受け入れるよう、必死に懇願しました。「私の命は、国家の非情な論理の犠牲になろうとしている」といった、政府の対応を批判する悲痛な言葉も含まれていました。実際に、ローマ教皇パウロ6世は、モーロの旧友として、個人的に赤い旅団に対して「アルド・モーロを無条件で解放するように」と、涙ながらに訴えかける公開書簡を発表しました。
しかし、当時の首相ジュリオ・アンドレオッティ率いるイタリア政府(それは皮肉にも、モーロが実現しようとした共産党の閣外協力を得て成立した政権でした)は、赤い旅団の要求に対して、終始一貫して極めて強硬な姿勢を取り続けました。政府は、「国家はテロリストの脅迫には絶対に屈しない」「テロリストと交渉することは、彼らの存在を認め、さらなるテロを助長することになる」という原則(これは「Linea della fermezza」、しばしば「非情路線」とも訳されます)を堅持し、赤い旅団とのいかなる直接交渉も、そして彼らが要求した囚人交換も、きっぱりと拒否し続けたのです。
このイタリア政府の「非情」とも言える対応については、当時から現在に至るまで、イタリア国内だけでなく、国際的にも大きな議論を呼んでいます。「テロに屈しないという国家の断固たる姿勢を示した、正しい判断だった」という支持の声がある一方で、「人質となった国民(しかも元首相)の命を最優先し、あらゆる可能性を探って交渉すべきだったのではないか」「政治的な計算や、モーロの『歴史的妥協』路線を快く思わない勢力の意向が働いた結果、彼は見殺しにされたのではないか」といった、政府の対応を厳しく批判する声も根強くあります。モーロが所属していた与党・キリスト教民主党内や、閣外から政権を支えていた共産党内でも、この対応を巡っては意見が大きく分かれ、イタリア政界に深い亀裂を残しました。
ローマの路上で… 悲劇的な結末(1978年5月9日)
政府が交渉を拒否し続けたため、「赤い旅団」はアルド・モーロ元首相を「人民裁判」にかけて有罪とし、死刑を宣告しました。イタリア当局は大規模な捜索を行ったものの、モーロの発見には至りませんでした。
誘拐から55日後、1978年の今日、5月9日。ローマの中心部、キリスト教民主主義(DC)の本部と、イタリア共産党(PCI)の本部が、それぞれ目と鼻の先にある、まさに「歴史的妥協」を象徴するかのような場所、カエターニ通りの路上に、一台の赤いルノー・4(当時のイタリアでよく見られた小型の乗用車)が不審な形で停められているのが発見されました。
警察が駆けつけ、恐る恐る車のトランクを開けると、そこには毛布にくるまれたアルド・モーロの遺体が横たわっていました。彼は、胸に10発以上もの銃弾を浴びて殺害されていたのです。赤い旅団は、モーロを殺害した後、その遺体を、彼が生涯をかけて推進しようとした「歴史的妥協」を象徴する二大政党の本部のちょうど中間地点に遺棄するという、極めて冷酷で、政治的なメッセージ性の強い行為に及んだのでした。
事件がイタリアと世界に残したもの
元首相であり、与党党首であったアルド・モーロが、テロリストによって誘拐され、政府が交渉を拒否する中で殺害されたという事実は、イタリアの戦後史において最も衝撃的で、最も悲劇的な事件として、人々の記憶に深く、そして永く刻まれることになりました。
イタリア社会への計り知れない衝撃
国民から広く尊敬を集め、「誠実な政治家」として知られていたモーロの、あまりにも惨い死は、イタリア国民全体に計り知れないほどの衝撃、悲しみ、そしてテロリズムに対する激しい怒りをもたらしました。同時に、人質の命よりも国家の原則を優先した政府の「非情」な対応に対する、疑問や不信感も広がりました。イタリア社会は、この事件によって深い傷を負い、その後の政治や社会のあり方に大きな影響を受け続けることになります。
政治への影響と陰謀論
モーロの死によって、彼が推進してきた「歴史的妥協」の構想は、完全に頓挫してしまいました。キリスト教民主党と共産党との間の協力関係は崩壊し、イタリア政治は再び不安定で、対立の激しい時代へと逆戻りしていきます。また、事件の真相を巡っては、その後何十年にもわたって、様々な憶測や陰謀論が語られ続けることになりました。例えば、
「政府の中枢に、モーロの死を望んでいた勢力がいたのではないか?」
「アメリカのCIAやソ連のKGBといった外国の情報機関が、歴史的妥協を阻止するために裏で糸を引いていたのではないか?」
「赤い旅団は、実は何者かに利用されていたのではないか?」
といった、様々な説が(多くは根拠不十分ながらも)繰り返し議論されてきました。事件の全容については、いまだに多くの謎が残されている、とも言われています。
赤い旅団の終焉へ
一方で、このアルド・モーロ殺害という、イタリア国民全体を敵に回すような残虐な行為は、皮肉にも赤い旅団自身の衰退を決定づける結果となりました。それまで一部の過激な学生や労働者の間に存在したかもしれない、彼らの行動への微かな共感や幻想は完全に消え去り、テロリズムに対する社会全体の断固たる非難の声が高まりました。これを機に、イタリア政府はテロ対策の法整備と捜査体制を大幅に強化し、警察による赤い旅団メンバーの逮捕が相次ぎました。組織は内部崩壊を起こし、1980年代には、その組織的なテロ活動はほぼ終焉を迎えることになります。モーロの死は、イタリアにおける極左テロ時代の終わりを早めるきっかけともなったのです。
世界への問いかけ:「テロに屈しない」とは?
モーロ誘拐事件におけるイタリア政府の「テロには屈しない、交渉はしない」という強硬な姿勢は、その後の世界各国における対テロ政策のあり方にも、大きな影響を与えました。人質の命を救うためには、テロリストの要求(たとえそれが不当なものであっても)に、ある程度応じるべきなのか? それとも、国家の原則を貫き、将来のテロを防ぐためには、断固として交渉を拒否すべきなのか? この事件は、人命と国家の威信・原則とを天秤にかける、極めて困難で倫理的な問いを、改めて世界中の国々に突きつけることになったのです。
まとめ:対話と妥協を求めた政治家の悲劇
1978年の今日、5月9日に、テロリストの凶弾に倒れたその遺体が発見された、イタリアの元首相アルド・モーロ。彼は、第二次世界大戦後のイタリアが直面した、イデオロギーの激しい対立、深刻な社会不安、そして「鉛の時代」と呼ばれるテロリズムの嵐という、極めて困難な時代の中で、対話と妥協という、民主主義の基本に立ち返ることで、国をまとめ、安定させ、そして前に進めようとした政治家でした。
彼が人生の最後に目指した「歴史的妥協」という、共産党との連携を含む大胆な試みは、冷戦下のイタリアにおいては画期的であり、その先見性や政治的な勇気を評価する声がある一方で、結果的に彼自身の命を奪う悲劇を招く一因ともなってしまいました。
アルド・モーロ誘拐・殺害事件は、イタリア現代史における最も暗く、そして深い傷跡として、今もなお人々の心に残っています。それは、政治的な暴力の非道さと悲劇、そしてテロリズムという脅威に、社会がどのように向き合うべきかという、重く、そして答えの出ない問いを、私たちに投げかけ続けているのです。
彼が目指した「対話」と「和解」の精神は、奇しくも彼が殺害されたことによって潰えたかに見えましたが、分断と対立が世界各地で深まる現代においてこそ、その価値と意味を、改めて問い直してみる必要があるのかもしれません。
※本記事では英語版、イタリア語版も参考にしました
















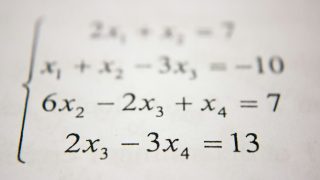






コメント