- 「人間動物園(Human Zoo)」とは、主に19世紀後半から20世紀初頭にかけて、ヨーロッパやアメリカ合衆国の博覧会、動物園、遊園地などで、アジア、アフリカ、南北アメリカの先住民といった非西洋の人々を、生きたまま「展示」し、見世物とした催しのことです。ドイツ語では「フェルカーシャウ(Völkerschau / 民族ショー)」とも呼ばれます。
- このような展示が行われた背景には、当時の植民地主義・帝国主義(欧米列強が世界を支配していた)、白人優越思想や歪んだ進化論に基づいた人種的偏見(非西洋民族を「未開」「野蛮」と見なす考え)、そして大衆の異国趣味や好奇心がありました。
- 展示された人々は、しばしば自分たちの故郷を「再現した」とされる囲いの中で、伝統的な衣装を着せられ、日常生活や儀式、踊りなどを演じることを強いられました。その扱いは動物園の動物と変わらないほど劣悪な場合も多く、人としての尊厳は無視されていました。
- パリ万博やセントルイス万博などでの大規模な展示や、興行師カール・ハーゲンベックによる「民族ショー」などが有名です。日本でも1903年の大阪万博で「人類館事件」という同様の問題が起こりました。
- 20世紀に入り、人権意識の高まりや植民地主義への批判などから、このような非人道的な見世物は次第に姿を消しましたが、過去の差別と搾取の歴史を象徴する「負の遺産」として、その過ちを繰り返さないために記憶されるべき出来事です。
動物園といえば、ライオンやゾウ、パンダなど、世界中の様々な動物たちの生き生きとした姿を間近に観察できる、子供から大人まで楽しめる人気のレジャースポットですよね。
しかし、今からほんの100年ほど昔、ヨーロッパやアメリカでは、動物ではなく、「人間」そのものが、まるで珍しい生き物のように「展示」され、多くの人々の見世物となっていたという、信じられないような時代があったことをご存知でしょうか?
それが、「人間動物園(Human Zoo)」、あるいはドイツ語で「フェルカーシャウ(Völkerschau / 民族ショー)」と呼ばれる、歴史の闇に葬り去りたいような、しかし決して忘れてはならない出来事です。
今回は、この現代の私たちの倫理観からは到底受け入れられない、しかし実際に欧米の主要都市で大人気を博した「人間動物園」とは一体どのようなものだったのか、その衝撃的な実態と、それが生まれた歴史的背景、そしてこの悲しい歴史が私たちに何を問いかけているのか、探っていきたいと思います。
「人間動物園」とは? 野蛮な見世物の実態
「人間動物園」と聞くと、まずその言葉の響きに強い不快感や嫌悪感を覚える方も多いでしょう。しかし、これは比喩表現ではなく、文字通り、人間が「動物園の展示物」のように扱われた歴史を指しています。
具体的には、主に19世紀後半から20世紀の前半(だいたい1870年代から1930年代頃がピークで、一部は1950年代まで続きました)にかけて、ヨーロッパの主要都市(パリ、ロンドン、ベルリン、ハンブルク、アントワープ、ブリュッセルなど)や、アメリカ合衆国の各地で開催された、博覧会(特に万国博覧会は格好の舞台となりました)、遊園地、動物園、あるいは独立した興行(サーカスのようなもの)において、
アジア、アフリカ、南北アメリカ大陸の先住民、オセアニアの島々の人々といった、いわゆる「非西洋」の民族の人々を、生きたまま「展示」し、多くの観客に見世物として提供した
という催しのことを指します。
展示の方法は様々でしたが、多くの場合、
- 展示される人々は、彼らの故郷の村や住居を「忠実に再現した」とされる(実際には主催者側の勝手なイメージで作られたことも多い)囲いや建物の中で生活させられました。
- 彼らは、自分たちの「伝統的」とされる衣装を常に身に着けることを強要され、
- 観客の前で、日常生活の様子(料理、子育て、工芸品の製作など)や、宗教的な儀式、歌や踊りなどを、繰り返し演じることを求められました。
- その扱いは、しばしば動物園の動物たちと何ら変わらないものでした。彼らは、まるで檻の中にいるかのように観客の好奇の視線にさらされ、時には食べ物を投げ与えられたり、嘲笑されたりすることもあったと言われています。衛生状態や食事、医療といった面でも、劣悪な環境に置かれることが少なくありませんでした。
- 時には、彼らの身体的な特徴(例えば、南アフリカのコイコイ族の女性であったサラ・バートマンの、当時のヨーロッパ人から見て「珍しい」とされた大きな臀部<でんぶ>や性器の形状など)が、ことさらに強調され、科学的な興味の対象であるかのように装いながら、実際には低俗な見世物として扱われる、という悲劇も起こりました。
なぜ人間が「展示」されたのか? その背景にあるもの
現代の私たちの倫理観や人権意識からすれば、このような「人間動物園」という行為は、到底理解しがたく、許されるものではありません。では、なぜ当時のヨーロッパやアメリカの社会では、このような見世物が公然と行われ、しかも多くの人々がそれを娯楽として楽しんでいたのでしょうか? その背景には、当時の時代状況が生み出した、いくつかの根深い要因がありました。
植民地主義と帝国主義の全盛期
19世紀後半から20世紀初頭は、ヨーロッパの列強(イギリス、フランス、ドイツ、ベルギー、オランダなど)や、新興国であったアメリカ合衆国が、アジア、アフリカ、太平洋の島々など、世界の広大な地域を植民地として次々と獲得・支配し、その資源や労働力を搾取していた「帝国主義」の時代でした。
「人間動物園」は、これらの植民地から「珍しい」「異国情緒あふれる」人々を連れてきて見せることで、宗主国(支配する側の国)の一般大衆に対して、自国の帝国の広大さ、多様さ、そしてその力を誇示するという、国威発揚のプロパガンダの役割も果たしていました。「我々はこれほど多くの、そしてこれほど『奇妙な』人々を支配しているのだ」というわけです。
人種的な偏見と「科学的」レイシズムの蔓延
当時のヨーロッパ社会には、
白人種が他の全ての人種よりも生物学的にも文化的にも優れており、世界の頂点に立つべき存在である
という「白人優越思想」が、疑う余地のない「真実」として広く浸透していました。
また、19世紀半ばにチャールズ・ダーウィンが発表した「進化論」は、生物学に革命をもたらしましたが、その理論が誤って、あるいは意図的に人間社会に適用され、
人間社会や人種にも『進化の段階』があり、白人(特にヨーロッパ人)はその最も進化した頂点に位置し、非西洋の有色人種はより『原始的』で『未開』で『劣った』段階にある
と考える、社会ダーウィニズムや、人種的階層論といった考え方(これらは現在では「科学的レイシズム」あるいは「疑似科学的人種差別」として厳しく批判されています)が、一部の学者や、そして一般大衆の間でも、大きな影響力を持っていました。
「人間動物園」は、まさにこの「未開」で「野蛮」とされる(とヨーロッパ人が勝手に決めつけた)人々を、「生きた標本」として展示することで、西洋文明がいかに「進歩」し、「優位」であるかを、観客に視覚的に、そして感情的に印象づけ、既存の人種的な偏見や差別意識をさらに強化・再生産する役割を果たしたのです。
大衆の好奇心と異国趣味(エキゾチシズム)
当時の一般のヨーロッパ人やアメリカ人にとって、アフリカの奥地や、アジアの秘境、あるいは太平洋の島々に住む人々の姿や生活様式は、まだほとんど知られていない、未知の世界でした。写真技術はまだ初期段階であり、映画やテレビはもちろん存在しません。旅行も一部の富裕層や探検家だけのものでした。
そのため、「生きた」異国の人々を、まるで動物園で珍しい動物を見るかのように、直接自分の目で見ることができるという「人間動物園」は、彼らの強い好奇心や、エキゾチックなものへの憧れ(異国趣味)を満たす、非常に刺激的で人気のあるエンターテイメント(見世物)として、大きな成功を収めたのです。
興行としての巨大なビジネス
そしてもちろん、このような大衆の需要があれば、そこにはビジネスチャンスが生まれます。動物園の経営者や、サーカスや見世物小屋の興行主たちにとって、「人間動物園」は、莫大な利益を生み出す新しい「商品」でした。
特に、ドイツのハンブルクを拠点とした有名な動物商であり、近代的な動物園(檻ではなく、より自然に近い環境で動物を展示する「ハーゲンベック式展示」を考案した)の父とも呼ばれるカール・ハーゲンベックは、動物の輸入・展示と並行して、1870年代から、サモア人、エスキモー(現在のイヌイット)、ヌビア人(アフリカ)、ラッブランド人(スカンジナビア北部のサーミ人)など、世界各地の民族をヨーロッパに連れてきて、「民族ショー(Völkerschau / フェルカーシャウ)」と名付けて巡業し、商業的に大成功を収めました。彼は、これらの展示を単なる見世物ではなく、「教育的」「科学的」なものであるかのように装いましたが、その実態は、やはり人々の好奇の目を満足させる興行であったと言わざるを得ません。
世界各地で行われた「展示」:歴史に残る悲劇の事例
「人間動物園」は、19世紀末から20世紀初頭にかけて、ヨーロッパの主要都市(パリ、ロンドン、ベルリン、ハンブルク、アントワープ、アムステルダム、ブリュッセル、ミラノなど)や、アメリカ合衆国の各地(ニューヨーク、シカゴ、セントルイス、フィラデルフィアなど)で、特に万国博覧会が開催される際には、その目玉となる展示の一つとして、繰り返し、そして大規模に行われました。
パリ万国博覧会(1878年、1889年、1900年、1931年など)

1889年にパリ万博の責任者に連れてこられた。
フランスが誇る広大な植民地(アフリカのセネガル村、インドシナの村、ポリネシアの村など)の風景や建物を「忠実に再現」し、そこに住む人々を、伝統的な衣装を着せ、伝統的な生活様式(踊り、儀式、工芸品の製作など)を演じさせながら「展示」しました。1889年のパリ万博(エッフェル塔が建設された万博です)では、その会場の一角に、なんと400人もの植民地出身の人々が「生きた展示物」として集められ、見世物にされたと言われています。
アメリカの万国博覧会

(出典:wikimedia commons)
アメリカでも同様の展示は盛んに行われました。特に、1904年に開催されたセントルイス万国博覧会では、アメリカが米西戦争(1898年)の結果、新たに植民地(保護領)としたフィリピンの様々な部族の人々(中でもイゴロット族の人々が、その「原始的な」生活様式を強調されて展示され、大きな話題となりました)が、「人類学的な展示」という名目で、大規模に見世物にされました。また、インディアン(ネイティブアメリカン)の部族や、アフリカのピグミー族のオタ・ベンガという青年が、一時期ブロンクス動物園のサル山で「展示」されたという、極めて非人道的な事件も起こっています。
カール・ハーゲンベックの「民族ショー」
前述のカール・ハーゲンベックは、単に人々を連れてきて見せるだけでなく、彼らの「日常生活」や「儀式」「狩りの様子」などを、よりリアルに、そしてドラマチックに再現させ、観客を魅了しました。彼は、これらの展示を「教育的」で「科学的」なものであると主張しましたが、その実態は、やはりエキゾチシズムとセンセーショナリズムを煽る、見世物としての性格が強かったと言わざるを得ません。
サラ・バートマン(「ホッテントット・ヴィーナス」)の悲劇

「人間動物園」の歴史の中でも、特に一個人の尊厳が徹底的に踏みにじられ、その悲劇性が際立っている事例として、19世紀初頭のサラ・バートマン(Saartjie Baartman)という南アフリカのコイコイ族(当時は「ホッテントット族」という、現在では差別的とされる呼称で呼ばれていました)の女性の物語があります。
彼女は、その大きな臀部(でんぶ)や、特異な形状とされた性器といった身体的特徴が、当時のヨーロッパ人にとって「珍しく」「野性的」と見なされ、イギリスやフランスに連れてこられました。そして、「ホッテントット・ヴィーナス」という見世物名で、ロンドンやパリの劇場、パーティー、さらには動物園のような場所で、半裸に近い姿で多くの人々の好奇の目にさらされ続けました。彼女は若くして(20代半ばで)亡くなりましたが、その悲劇は死後も続きました。彼女の遺体は解剖され、その脳や性器はホルマリン漬けにされ、骨格標本と共に、パリの博物館(人類博物館など)に、科学的な「標本」として、なんと20世紀後半まで展示され続けたのです。彼女の遺骨が、長年の抗議と交渉の末に、ようやく故郷南アフリカに返還され、尊厳をもって再埋葬されたのは、21世紀に入ってからの2002年のことでした。サラ・バートマンの物語は、植民地主義と科学的レイシズムが、いかに一個人の人権を蹂躙(じゅうりん)しうるかを示す、痛ましい象徴となっています。
日本における「人類館事件」
実は、このような「人間を展示する」という行為は、遠い欧米だけの話ではありませんでした。日本でも、これと非常によく似た、そして大きな社会問題となった出来事があったのです。
1903年(明治36年)に大阪で開催された第5回内国勧業博覧会(当時の日本で最大の博覧会)の会場内に、「学術人類館」と名付けられたパビリオンが設けられました。そこでは、日本の帝国統治下にあった、あるいは関わりの深かった地域の人々――アイヌ、沖縄(琉球人)、台湾先住民(高砂族など)、朝鮮人、中国人、インド人、ジャワ人など――が、それぞれの「伝統的な」とされる住居や生活様式と共に、「生きた展示物」として見世物にされたのです。
主催者側は、これを「学術研究のため」「風俗比較のため」と説明しましたが、実際には多くの人々が、珍しいものを見るような、あるいは差別的な好奇の目でこれらの人々を見物し、大きな「人気」を博しました。しかし、この展示に対しては、特に沖縄県や朝鮮半島出身の人々や知識人から、
我々を動物扱いするとは何事か!人間の尊厳を著しく傷つけるものだ!
という、当然の、そして激しい抗議の声が上がり、大きな社会問題(「人類館事件」と呼ばれます)となりました。これもまた、当時の日本の帝国主義的な拡大と、他のアジア民族に対する優越感や差別的な眼差しが生み出した、歴史の負の側面を象徴する出来事と言えるでしょう。
非人道的な見世物の終わり:人権意識の高まりと共に
このような、人間を「展示物」として扱う「人間動物園」や「民族ショー」といった見世物は、19世紀末から20世紀初頭にかけて、ヨーロッパやアメリカで大きな人気を博しましたが、その一方で、当初から一部の知識人や人道主義者たちからは、その非人道性や人種差別的な性質に対する批判の声も上がっていました。
そして20世紀に入ると、いくつかの大きな社会的な変化の中で、このような展示は次第に時代遅れで、受け入れられないものという認識が広まっていきます。
- 倫理的な問題への気づき
人間を、まるで動物園の動物のように、その意志や感情を無視して「展示」し、見世物にするという行為そのものが、人間の尊厳を根本から踏みにじる、非倫理的な行為である、という認識が、徐々にではありますが、社会に浸透していきました。 - 展示された人々の苦難と抵抗
展示された人々の多くは、故郷から遠く離れた、言葉も通じない異国の地で、不慣れな気候や食事、そして常に好奇の視線にさらされるという、大きな精神的・肉体的ストレスの中で生活することを強いられました。彼らは、契約に基づいて金銭を得ていたケースもありますが(その契約が公正なものであったかは疑問ですが)、中には騙されたり、半ば強制的に連れてこられたりした人々もいたとされています。劣悪な衛生環境や、不十分な医療体制、そして故郷とは異なる気候や食事に適応できず、病気にかかったり、若くして亡くなってしまったりする人も少なくありませんでした。また、展示されることへの屈辱感から、抵抗したり、逃亡を試みたりする人もいたと言われています。 - 人権意識の世界的向上と反植民地主義
20世紀を通じて、特に二度の世界大戦(その原因の一つには帝国主義と人種差別もありました)を経て、世界的に基本的人権という考え方が重視されるようになり、またアジアやアフリカの多くの植民地で独立運動が活発化し、植民地支配そのものの不当性が広く認識されるようになりました。これに伴い、人種差別の不当性についても、国際的なコンセンサスが形成されていきました。 - 人類学という学問の発展
また、異文化を研究する学問である人類学も、20世紀に入ると大きく発展しました。かつては、異文化を「未開」「野蛮」なものとして、ヨーロッパ中心的な視点から見下すような傾向(進化主義など)もありましたが、次第に、それぞれの文化が持つ独自の価値や多様性を尊重し、その文化の内側から客観的に理解しようとする姿勢(文化相対主義など)が主流となっていきました。これにより、「人間動物園」のような、異文化を一方的に見世物にする行為の、学術的な正当性も失われていったのです。
こうした社会全体の意識の大きな変化の中で、「人間動物園」のような、露骨に差別的で非人道的な見世物は、次第に時代遅れで、そして社会的に受け入れられないものとなっていきました。特に第二次世界大戦後、多くの植民地が次々と独立を達成していく中で、人間動物園は急速にその姿を消していきました。

記録に残る、あるいは最も有名とされる最後の「人間動物園」の事例は、1958年にベルギーの首都ブリュッセルで開催された万国博覧会で設けられた「コンゴ村(Congolese village)」の展示です。そこでは、当時のベルギー領コンゴ(現在のコンゴ民主共和国)から連れてこられたコンゴの人々が、彼らの「伝統的な」生活を再現して「展示」されました。しかし、この展示に対しても、国内外から多くの批判が寄せられ、人権侵害であるとの声が高まりました。これが、大規模な人間動物園の、事実上の終焉となったと言われています。
「人間動物園」が現代に問いかけるもの:歴史の教訓を忘れない
今日の私たちの目から見れば、あまりにも野蛮で、非人道的で、そして差別的としか言いようのない見世物であった「人間動物園」。それは、植民地主義、帝国主義、そして人種差別という、19世紀から20世紀初頭にかけての世界を覆っていた、暗く、そして重い歴史の「負の遺産」そのものです。
この忌まわしい歴史を振り返ることは、私たちに多くの、そして重要な教訓を与えてくれます。
- 他者を見る「まなざし」の問題
私たちは、自分たちとは異なる文化や、異なる外見、異なる価値観を持つ人々に対して、無意識のうちに「珍しいもの」「奇妙なもの」「理解できないもの」、あるいは「劣ったもの」として見てしまうような、差別的で一方的な「まなざし」を持っていないだろうか? - 「科学」と「差別」の危険な結びつき
かつて「科学的」な言説としてまかり通っていた人種理論(社会ダーウィニズムや優生学など)が、いかに容易に人種差別を正当化し、非人道的な行為(人間動物園もその一つです)を助長しうるか、という危険性。 - エンターテイメントと倫理の境界線
人々の好奇心を満たし、娯楽を提供するためであれば、他者の尊厳や人権を傷つけても良いのか? エンターテイメントが持つべき倫理的な境界線はどこにあるのか? - 歴史の「暗部」と向き合い、記憶することの重要性
私たちの社会が、過去にどのような過ちを犯してきたのかを正直に見つめ、そこから学び、同じ過ちを二度と繰り返さないようにする努力がいかに大切か。
「人間動物園」という現象は、決して遠い過去の、特殊で野蛮な時代だけの出来事として片付けてしまえるものではありません。それは、形を変えながらも、現代社会にも依然として潜んでいるかもしれない、他者への無理解、偏見、差別、そして権力を持つ側による搾取といった、普遍的な問題について、私たちに深く考えさせる、重い問いを投げかけ続けているのです。
まとめ:忘れられた歴史の教訓を、未来への光へ
かつて、私たちの祖先の時代には、肌の色や文化が違うというだけで、人間がまるで動物のように檻に入れられ、「展示」され、見世物にされるという、信じがたいことが、文明国とされた国々で公然と行われていました。「人間動物園」あるいは「民族ショー」と呼ばれたこれらの催しは、植民地主義と人種的偏見が色濃く影を落としていた時代の、暗く、そして恥ずべき側面を象徴するものでした。
アジアの、アフリカの、アメリカ大陸の、そして太平洋の島々の人々が、故郷から遠く引き離され、ヨーロッパやアメリカの華やかな都市へと連れてこられました。そしてそこで、彼らは「未開の野蛮人」「珍しい見世物」として、大衆の好奇の目にさらされ、時にはその尊厳を深く傷つけられ、人間としての基本的な権利さえも踏みにじられました。
このような非人道的な見世物は、幸いにも20世紀半ばには、人権意識の高まりと共に、ほぼ完全に姿を消しました。しかし、それが実際に存在したという事実と、それがなぜ可能であったのかという歴史的背景を、私たちは決して忘れてはなりません。
「人間動物園」の歴史を知ることは、私たち人類が過去に犯した過ちから学び、将来、同じような過ちを二度と繰り返さないために、そして多様な文化や価値観を持つ全ての人々が、互いの尊厳を尊重し合い、共生していける、より公正で、より人間的な社会を築いていくために、極めて重要な教訓を与えてくれるのではないでしょうか。
忘れられた歴史の教訓を、未来を照らす光へと変えていくこと。それが、この悲しい歴史と向き合う、現代に生きる私たちに課せられた責任なのかもしれません。
※本記事では英語版、ドイツ語版も参考にしました








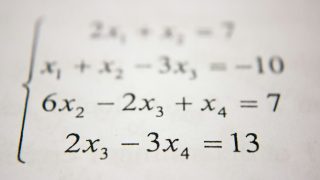













コメント