- 「ヘンペルのカラス」とは、「全てのカラスは黒い」という仮説を確かめる(確証する)方法について考えた時に生じる、一見奇妙な、しかし論理的には正しそうに見えるパラドックス(逆説)のことです。20世紀の科学哲学者カール・ヘンペルが提唱しました。
- 普通に考えれば、「全てのカラスは黒い」ことを確かめるには、「黒いカラス」をたくさん見つけるのが良い方法ですよね。
- ところが、論理学の「対偶(たいぐう)」という考え方を使うと、「全てのカラスは黒い」という主張は、「黒くない全てのものは、カラスではない」という主張と全く同じ意味(同値)になります。
- では、「黒くない全てのものは、カラスではない」ことを確かめるにはどうすればいいか? 例えば、「赤いリンゴ」(黒くなくて、カラスでもないもの)を見つけることが、この主張を少し強めることになります。
- ここで問題が起こります。もし「赤いリンゴ」が「黒くない全てのものはカラスではない」を強めるなら、それと論理的に同じ意味である「全てのカラスは黒い」という主張もまた、「赤いリンゴ」によって(ほんの少しでも)強められることになってしまうのでは…? でも、リンゴを見たからといって、カラスの黒さについての確信が深まるなんて、私たちの直観には全く合いませんよね?
- この「論理的にはそうかもしれないけど、感覚的にはおかしい!」というズレが、ヘンペルのカラスのパラドックスの面白さであり、科学における「証拠」や「確証」とは何かを深く考えさせる、有名な思考実験となっています。
「カラスは黒い」――これは、私たちの多くが、日々の経験や見聞から「まあ、そうだろうな」と納得している「事実」の一つですよね。
では、もしあなたが科学者で、この「全てのカラスは、本当に黒いのか?」という仮説を、もっと厳密に確かめたい(これを「確証する」と言います)と考えたとしましょう。あなたなら、どんな証拠を集めますか?
おそらく、まず思いつくのは、「実際にカラスをたくさん観察して、その色が黒いことを一つ一つ確認していく」という方法でしょう。「あ、このカラスも黒い」「こっちのカラスも黒いぞ」……と、「黒いカラス」の観察例が増えれば増えるほど、「全てのカラスは黒い」という仮説は、より確からしいものになっていくように感じられます。これは、ごく自然で、直観的にも分かりやすい考え方ですよね。
ところが、ここに論理学という道具を持ち込むと、事態は少し奇妙な方向へと進んでしまうのです。そして現れるのが、科学哲学の世界で長年議論されてきた有名なパラドックス(逆説、一見すると正しそうなのに、よく考えると矛盾やおかしな結論に至ってしまう問題)、「ヘンペルのカラス(Hempel’s paradox / Raven paradox)」です。
なんとこのパラドックスに従うと、「赤いリンゴを見た」という、カラスとは全く関係なさそうな観察でさえも、「全てのカラスは黒い」という仮説を(ほんのちょっぴりだけ)強める証拠になってしまう……というのです!
「え、どういうこと!? リンゴとカラスに何の関係が?」と混乱してしまいますよね。今回は、この一見すると奇妙で、しかし論理の迷路に私たちを誘い込む、「ヘンペルのカラス」のパラドックスの世界に、足を踏み入れてみましょう。
「全てのカラスは黒い」を証明するには? 基本の考え方
この興味深いパラドックスを私たちに提示してくれたのは、20世紀にドイツからアメリカへ渡って活躍した、著名な科学哲学者カール・グスタフ・ヘンペル(Carl Gustav Hempel)です。彼は1940年代に、私たちが科学的な法則や仮説をどのようにして「確かめていく(確証していく)」のか、その論理的な仕組みや問題点について、深く考察していました。
まず、ヘンペルは、議論の出発点として、非常にシンプルで、誰もが理解しやすい次のような命題(真か偽かを判断できる主張のこと)を考えました。
全てのカラスは、黒い色をしている。 (All ravens are black.)
さて、この命題Pが正しいということを、私たちはどのようにして確かめていく(確証していく)ことができるでしょうか?
普通に考えれば、次のような観察例が、命題Pの「確からしさ」を高めてくれると考えられます。
- 観察例1:「黒いカラス」を一羽、森で見つけた。
→ これにより、命題P「全てのカラスは黒い」は、少しだけ強まった(確証された)ように思えますね。 - 観察例2:さらに別の場所で、また「黒いカラス」を一羽見つけた。
→ これもまた、命題Pを少し強めてくれそうです。 - 観察例3:動物園で飼われているカラスも、やっぱり黒かった。
→ これも、命題Pを支持する証拠の一つと言えそうです。
このように、命題Pに合致する事例(この場合は「黒いカラス」)を一つ一つ観察し、その数を増やしていくことで、命題Pの「確からしさ(確証度)」が、少しずつ、しかし着実に高まっていく。これが、科学における証拠の集め方の基本的な考え方の一つ、いわゆる「帰納的な推論(きのうてきなすいろん)」と呼ばれるものです。ここまでは、特に難しいことはなく、私たちの日常的な感覚とも一致しますよね。
論理のトリック? 「対偶(たいぐう)」という考え方の登場
ところが、ここでヘンペルは、論理学という、思考のルールを探求する学問の道具を持ち込んできます。論理学には、「対偶(たいぐう / Contraposition)」という非常に重要な考え方があります。
ある命題(例えば、「AならばBである」)とその対偶命題は、論理的に全く同じこと(同値 / logically equivalent)を言っている
というのが論理学の基本的なルールの一つです。
では、先ほどの命題P「全てのカラスは、黒い色をしている。」の対偶をとると、どのような命題になるでしょうか?
「全てのカラスは黒い」という命題は、言い換えると「もし何かがカラスであるならば、それは黒い色をしている」と表現できますね。この対偶は、
もし何かが黒い色をしていなければ、それはカラスではない。
となります。これをもう少し自然な日本語にすると、
黒くない全てのものは、カラスではない。 (All non-black things are non-ravens.)
となります。
ちょっと分かりにくいかもしれませんが、落ち着いて考えてみてください。命題P「全てのカラスは黒い」と、命題Q「黒くない全てのものはカラスではない」は、言っている内容は全く同じだということがお分かりいただけるでしょうか?
もし「黒くないのにカラスであるもの(例えば、白いカラス)」が一羽でも存在したら、最初の命題P「全てのカラスは黒い」は間違っていたことになりますよね。逆に、命題Pが正しい(全てのカラスが本当に黒い)のであれば、何か黒くないものを見つけた時、それは絶対にカラスではありえないはずです。
このように、命題Pと命題Qは、表現の仕方が違うだけで、論理的には全く同じことを主張している「同値な命題」なのです。
さて、ここからが重要です。もし命題Pと命題Qが論理的に同じこと(同値)を言っているのであれば、命題Qを確証する(より確からしくする)ような観察例は、同時に、命題Pも確証する(より確からしくする)はずですよね? 同じことを言っている二つの主張なのですから。
では、命題Q「黒くない全てのものは、カラスではない。」を確証する観察例とは、具体的にどのようなものでしょうか? それは、文字通り、「黒くなくて、かつ、カラスではないもの」を見つけることです。例えば……
- 観察例3:「赤いリンゴ」を一つ見つけた。
→ リンゴは「黒くない」ですよね。そして、リンゴは「カラスではない」ですよね。したがって、「赤いリンゴ」は、命題Q「黒くない全てのものは、カラスではない。」に合致する観察例と言えます。 - 観察例4:「白い靴」を一足見つけた。
→ これも、「黒くないもの」であり、かつ「カラスではない」ので、命題Qに合致します。 - 観察例5:「緑色の葉っぱ」を一枚見つけた。
→ これも同様です。
つまり、私たちの身の回りに存在する、およそ「黒い色をしていなくて、かつ、カラスという鳥ではないもの」を観察することは、全て、命題Q「黒くない全てのものは、カラスではない。」を確証していく(その確からしさを少しずつ高めていく)ことになるはずです。
パラドックスの誕生:赤いリンゴが「カラスは黒い」を証明する!?
さあ、いよいよパラドックスの核心部分に迫ってきました。ここまでの話を整理してみましょう。
- 前提1
命題P「全てのカラスは黒い」を確証する(より確からしくする)のは、「黒いカラス」を観察することである。 - 前提2
命題P「全てのカラスは黒い」と、その対偶である命題Q「黒くない全てのものはカラスではない」は、論理的に全く同じこと(同値)を言っている。 - 前提3
命題Q「黒くない全てのものはカラスではない」を確証するのは、「赤いリンゴ」や「白い靴」といった、「黒くなくて、かつ、カラスではないもの」を観察することである。
これらの前提から、論理的に導き出される結論は何でしょうか?
論理的な帰結
もし命題Pと命題Qが論理的に同じことを言っているのであれば、命題Qを確証するものは、命題Pもまた確証するはずです。 ということは、「赤いリンゴを見た」という観察は、「全てのカラスは黒い」という命題の確からしさを(たとえほんのわずかであったとしても)高めることになるはずだ……!?
しかし、これは私たちの日常的な直観や常識とは、全く合いませんよね!
普通に考えて、あなたが「カラスは本当に黒いのか?」ということを確かめたいと思っている時に、誰かが
おい、今、庭で真っ赤なリンゴがなっているのを見たぞ! これでまた一つ、『カラスは黒い』という説が強まったな!
なんて言ってきたら、あなたはどう思いますか?
「何を言っているんだ? リンゴの色とカラスの色に何の関係があるんだ?」と、きっと首をかしげるでしょう。
また、カラスの色について調べたいなら、カラスそのものを観察しに行くべきであって、カラスとは全く関係のない、そこらじゅうにあるリンゴや靴や葉っぱをいくら観察しても、「カラスは黒い」という確信が深まるなんてことは、到底ありえないように感じます。
この、論理的な推論を丁寧に積み重ねていくと、一見正しい結論(「赤いリンゴ」も「カラスは黒い」を確証する)にたどり着くように見えるのに、その結論が私たちの直観や常識とは著しく食い違ってしまう、という点が、「ヘンペルのカラス」が「パラドックス」と呼ばれる理由なのです。論理は正しいはずなのに、なぜかおかしな結論が出てしまう……。
なぜこんなおかしなことになる? 様々な解決の試み
この奇妙で、頭を悩ませる「ヘンペルのカラス」のパラドックスは、発表されて以来、科学哲学の世界で大きな議論を巻き起こしてきました。それは、単なる言葉遊びや論理パズルではなく、私たちが「科学的な証拠」とは何か、「仮説を確証する」とはどういうことなのか、そして「帰納的な推論」という科学の基本的な方法が持つ根本的な問題点について、深く考えさせるテーマを含んでいるからです。
多くの哲学者や科学者が、このパラドックスを何とか「解決」し、私たちの直観と論理の間のズレを埋めようと、様々な説明や反論を試みてきました。そのうちのいくつか代表的な考え方をご紹介しましょう。
ヘンペル自身の考え(論理的には正しい、でも確証度は極小)
このパラドックスを最初に提示したヘンペル自身は、最終的には、
私たちの直観には反するかもしれないが、論理的な整合性を考えるならば、『赤いリンゴを見た』という観察も、ごくごく僅(わず)かながらではあるが、『全てのカラスは黒い』という命題を確かに確証している、と認めざるを得ない
という立場を取りました。 ただし、彼が強調したのは、その確証の「度合い」や「強さ」です。「黒いカラスを1羽見つける」という観察が「全てのカラスは黒い」という仮説に与える確証の度合いに比べて、「赤いリンゴを1個見つける」という観察が与える確証の度合いは、比較にならないほど、無視できるほど小さいのだ、と考えました。私たちの直観が「リンゴを見てもカラスのことは何も分からない」と感じるのは、その確証度があまりにも小さすぎて、実質的にゼロに近いからかもしれません。
ベイジアン(確率論的)なアプローチ:証拠の「意外性」と「情報量」が重要
より現代的で、多くの人に受け入れられやすい解決策の一つとして有力視されているのが、ベイズ統計学という確率の考え方を用いたアプローチです。この考え方では、
ある証拠(観察例)が、ある仮説の「確からしさ」(確率)をどれだけ上昇させるか(つまり、どれだけ強く確証するか)は、いくつかの要因、特に
・その証拠がどれだけ「珍しい」か、
・あるいは「意外」か、
・そしてその証拠がその仮説をどれだけ強く支持するか(情報量が多いか)
といったことに左右される
と考えます。
「全てのカラスは黒い」という仮説について考えてみましょう。
もし私たちが「黒いカラスを一羽見た」という証拠を得たとします。これは、仮説に直接関係する、比較的情報量の多い証拠と言えます。そして、もし「カラスの中には白いものもいるかもしれない」と少しでも考えていたなら、「黒いカラス」の観察は、仮説の確からしさをある程度高めてくれるでしょう。
では、「赤いリンゴを見た(=黒くなくてカラスでないものを見た)」という証拠はどうでしょうか? 世の中には、「黒くなくて、かつ、カラスではないもの」は、赤いリンゴ以外にも、白い壁、青い空、黄色いバナナ、茶色い机…と、文字通り無限に近いほど、おびただしい数存在します。その中から「赤いリンゴ」という一つの事例を観察したとしても、それは「全てのカラスは黒い」という仮説の確からしさ(確率)を、ほとんど全く上昇させません。なぜなら、そのような観察はあまりにも「当たり前」であり、「意外性」が全くなく、仮説に関する新しい「情報」をほとんど何も与えてくれないからです。
このように、ベイズ主義的な考え方を用いると、「赤いリンゴ」の観察も、形式的には対偶命題を確証するかもしれませんが、その確証の「度合い」は限りなくゼロに近いため、「そんな観察はカラスの黒さとは関係ない」という私たちの直観と、うまく折り合いをつけることができる、と説明されます。
確証の対象を「カラス」に限定する考え方
もっとシンプルに、
『全てのカラスは黒い』という命題は、そもそも『カラス』という特定の種類の鳥について述べているのだから、それを確かめるためには、カラスそのものを観察しなければ意味がない。カラス以外のもの(リンゴや靴や葉っぱなど)をいくら調べたところで、それはこの命題の確証とは全く関係ないはずだ。
という、より直接的な反論もあります。つまり、確証のための観察は、その命題が直接言及している対象(この場合はカラス)に限定されるべきだ、という考え方です。
「自然種」という概念からのアプローチ
哲学の世界には、「自然種(Natural kind)」という考え方があります。これは、
宇宙や自然界に、人間が勝手に分類したのではなく、それ自体として意味のある「まとまり」や「種類」が存在する
という考え方です。「カラス」という鳥の種類や、「黒い」という色の性質は、ある程度「自然種」に近い、意味のある分類と言えるかもしれません。しかし、「カラスでないもの」や「黒くないもの」というのは、あまりにも範囲が広すぎて、ありとあらゆる雑多なものの寄せ集めであり、それ自体を一つの意味のあるグループとして扱うことには、科学的な意味がないのではないか、という指摘もあります。
パラドックスが教えてくれること:科学と論理、そして直観の不思議
「ヘンペルのカラス」のパラドックスは、完全に「はい、これで解決しました!」と誰もが納得するような、最終的な答えが出ているわけではなく、今なお科学哲学の教科書などで取り上げられ、議論される興味深いテーマです。
しかし、この一見するとただの言葉遊びや、論理のパズルのように思えるパラドックスは、私たちにいくつかの重要なことを教えてくれます。
論理の力と、その限界
論理的な推論は、私たちが物事を正確に考え、矛盾のない結論を導き出すための、非常に強力な道具です。しかし、その論理的に正しいはずの推論が、必ずしも私たちの日常的な直観や、常識的な感覚と一致するとは限らない、ということをこのパラドックスは示しています。
「確証」という概念の奥深さ
ある仮説が「確証された(より確かになった)」とは、一体どういうことなのでしょうか? どのような証拠が、どれくらいの強さで、仮説を支持すると言えるのでしょうか? このパラドックスは、科学的な推論のまさに土台にある「確証」という概念が、実は非常に複雑で、一筋縄ではいかない難しい問題を含んでいることを、私たちに気づかせてくれました。
科学の方法について考えるきっかけ
ヘンペルのカラスは、科学者たちが日々どのようにして仮説を立て、証拠を集め、実験や観察を通じて理論を検証し、新しい知識を築き上げていくのか、その「科学の方法」の根底にある論理的な問題点や、私たちが無意識に頼っている前提について、改めて深く考えるきっかけを与えてくれる、非常に優れた思考実験なのです。
まとめ:「カラスが黒い」はリンゴで証明できる……かも?
「全てのカラスは黒い」という、当たり前のように思えることを確かめるために、あなたはわざわざ庭に出て、赤いリンゴがなっているかどうかを確認しに行きますか? きっと、そんなことはしないでしょうし、そんなことをしても意味がない、と感じるはずです。
しかし、論理学の少し不思議な迷宮に足を踏み入れてみると、「赤いリンゴ」の観察もまた、遠い世界のカラスの黒さという仮説を、ほんの僅か、限りなくゼロに近いかもしれないけれど、確かに「確証」している「かもしれない」…という、私たちの直観とはかけ離れた、奇妙な結論が導き出されてしまう。
それが、「ヘンペルのカラス」のパラドックスが私たちに突きつける、面白くて、そしてちょっぴり頭が混乱するような問いかけなのです。
このパラドックスは、私たちがいかに日頃、「当たり前」の感覚に基づいて物事を判断しているか、そして「知る」ということ、「確かめる」ということの奥深さや複雑さを、少しユーモラスに、そして深く哲学的に、私たちに教えてくれているのかもしれませんね。
次にカラスを見かけたら、あるいはリンゴを手に取った時に、ふとこの「ヘンペルのカラス」の話を思い出してみるのも、日常の中に潜む「知的な面白さ」を発見する、良いきっかけになるかもしれませんよ。
※本記事では英語版も参考にしました












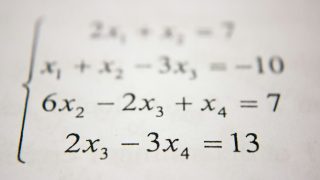









コメント