- 偽ドミトリー1世は、17世紀初頭のロシアが大混乱に陥った「動乱時代(スムータ)」に突如として現れた、謎に包まれた人物です。彼の正体は、モスクワから逃亡した修道士グリゴリー・オトレピエフであるという説が最も有力です。
- 彼は、かつて幼くして謎の死を遂げたはずの、イヴァン雷帝の末息子「ドミトリー皇子」であると自称しました。そして、ロシアと対立していた隣国ポーランド・リトアニア共和国の貴族たちの支援を受けて、ロシアに攻め込みました。
- 当時のロシアは、正統な王朝(リューリク朝)が途絶え、ツァーリ(皇帝)となったボリス・ゴドゥノフへの不満が高まっていた時期でした。「本物の皇子が生きていた!」という噂は民衆の期待を集め、ゴドゥノフの急死も重なり、偽ドミトリーは1605年にモスクワに入城し、なんと本物のツァーリとして即位してしまいます。死んだ皇子の母親も、彼を息子だと認めました。
- しかし、皇帝となった彼のポーランド風の振る舞いや、外国人を重用する姿勢は、ロシアの貴族や民衆の強い反感を買い、わずか11ヶ月ほどの治世の後、1606年に貴族ヴァシーリー・シュイスキーらが起こした反乱によって惨殺されるという、劇的な最期を遂げました。ロシア史上、最も有名で数奇な運命を辿った「なりすまし皇帝」です。
ロシアの歴史には、「スムータ」、日本語で「動乱」と呼ばれる、国全体が深い混乱と無秩序に陥った、暗く激しい時代があります(おおよそ1598年から1613年頃)。この時代には、国の根幹を揺るがすような、信じられない出来事が次々と起こりました。中でも特に奇妙で劇的なのが、「死んだはずの皇子」を名乗る人物が次々と現れ、あろうことかそのうちの一人が、本当にロシアの皇帝(ツァーリ)の座にまで登りつめてしまった、という事件です。
その最初の、そして最も有名な「なりすまし皇子」が、「偽ドミトリー1世」と呼ばれる人物です。彼は一体何者で、どのようにしてロシア皇帝の座を掴み、そしてなぜその座をすぐに失うことになったのでしょうか? ロシア史に特異な光芒(あるいは異様な影)を放つ、この謎多き僭称者(せんしょうしゃ=身分や地位を偽って名乗る者)の物語を紐解いていきましょう。
リューリク朝の断絶と動乱の幕開け
偽ドミトリー1世が登場する舞台背景には、まずロシアにおける正統な王朝の断絶という、国家の根幹に関わる大事件がありました。1598年、モスクワ大公国(後のロシア・ツァーリ国)を約700年にわたって統治してきたリューリク朝の最後のツァーリ、フョードル1世(彼は、恐怖政治で悪名高いイヴァン4世、通称「雷帝」の息子でしたが、父とは対照的に信仰心が厚く、政治にはあまり関心のない人物でした)が、世継ぎを残さないまま亡くなってしまったのです。
これにより、ロシアは後継者問題を巡って不安定な状況に陥ります。最終的に、フョードル1世の皇后イリナの兄であり、摂政として長年政治の実権を握っていた有力な大貴族(ボヤーレ)、ボリス・ゴドゥノフが、全国から代表者を集めた会議(ゼムスキー・ソボル)での選挙を経て、新たなツァーリとして選出されました(ゴドゥノフ朝の始まり)。
しかし、ボリス・ゴドゥノフの治世は多難な船出となります。彼は有能な政治家でしたが、もともとリューリク朝の血を引く王族ではなかったため、その正統性には常に疑問符が付きまといました。さらに、彼の治世下でロシアは未曽有の大飢饉(1601年~1603年)に見舞われ、多くの人々が餓死し、農奴制の強化も相まって、民衆の不満は日に日に高まっていきました。また、古くからの名門貴族の中には、成り上がり者のゴドゥノフがツァーリとなったことを快く思わず、虎視眈々と政権転覆の機会を窺っている者たちもいました。
そして、人々の間に根強く燻っていたのが、リューリク朝最後の男子相続人であった可能性のある、ドミトリー皇子(イヴァン雷帝の末息子で、フョードル1世の異母弟)の謎めいた死に関する疑惑でした。ドミトリー皇子は、1591年に流刑先のウグリチという町で、まだ9歳という若さで亡くなっていました。公式な調査報告では、てんかんの発作中にナイフで遊んでいて誤って自分の喉を突いてしまった「事故死」と結論付けられました。しかし、「将来のツァーリ候補であるドミトリー皇子を、権力を狙うボリス・ゴドゥノフが邪魔に思い、暗殺したのではないか?」という黒い噂が、ゴドゥノフがツァーリとなった後も、まことしやかに囁かれ続けていたのです。
「私はドミトリー皇子だ!」謎の青年現る
このような、正統な王朝への郷愁と、現政権への不満、そして皇子暗殺疑惑という、まさに火種がくすぶる状況の中に、1603年頃、一人の謎めいた青年が歴史の舞台に登場します。彼は、ロシアの西隣に位置する大国、ポーランド・リトアニア共和国の領内に現れ、驚くべき主張を始めました。
私は、ウグリチで死んだとされているドミトリー皇子本人である。あの時、私はボリス・ゴドゥノフの送った刺客から奇跡的に逃れ、修道院に身を隠し、生き延びてきたのだ! 私こそが正統なロシアのツァーリ位継承者である!
この「自称ドミトリー皇子」、歴史上「偽ドミトリー1世」と呼ばれることになるこの青年の本当の正体は、実はいまだに完全には解明されていません。しかし、最も広く受け入れられている説は、彼がモスクワのチュドフ修道院という有名な修道院から逃げ出した、グリゴリー・オトレピエフ(通称グリーシュカ)という名の若い修道士であった、というものです。
このオトレピエフという人物は、単なる修道士ではなく、読み書きができ、ある程度の教養と知識を持ち合わせていたようです。また、一時期、後にロシア皇帝となるロマノフ家など、モスクワの大貴族の屋敷に出入りしていたこともあり、宮廷の事情やドミトリー皇子のことについても詳しかったのではないか、と言われています。彼が自らの野心から、あるいはロマノフ家のような反ゴドゥノフ派の貴族に唆(そそのか)されて、この大胆不敵な「皇子なりすまし」計画を実行に移したのではないか、と考えられているのです。(他にも、彼こそが本物のドミトリーだった、あるいはイヴァン雷帝の隠し子だった、ポーランド貴族が送り込んだ替え玉だった、など様々な説がありますが、確たる証拠はありません。)
ポーランドの支援とロシアへの侵攻
この「奇跡的に生き残ったロシア皇子」を名乗る青年の出現は、当時ロシアと領土問題などで対立関係にあったポーランド・リトアニア共和国の有力者たちにとって、まさに渡りに船でした。特に、イェジー・ムニシェクのような野心的な大貴族(マグナート)たちは、偽ドミトリーを政治的に利用しようと考えます。彼を支援してロシアのツァーリの座に就けさえすれば、見返りとしてロシア西部の広大な領土(スモレンスクなど)を獲得し、さらにロシアにおけるポーランドの影響力を強めることができる、と画策したのです。また、敬虔なカトリック教国であるポーランドとしては、正教会が国教であるロシアをカトリック化するという宗教的な野心も持っていました。
偽ドミトリーは、このポーランド貴族たちの支援を取り付けるために、彼らにとって有利な約束を次々と結びました。ツァーリになった暁には、要求された領土を割譲すること、ロシアにカトリックを布教させること(彼自身、ポーランド滞在中に秘密裏にカトリックに改宗したとされています)、そして支援の中心人物であるイェジー・ムニシェクの美しく野心的な娘、マリーナ・ムニシェクと結婚すること、などです。
こうしてポーランドからの支援(ただし、ポーランド国王自身は公式な支援は表明しませんでした)を取り付けた偽ドミトリーは、1604年の秋、ポーランド人やリトアニア人の義勇兵、そしてウクライナ地方のコサックなどを中心とする、数千人規模の私兵集団を率いて、ロシアの国境を越え、モスクワを目指して侵攻を開始しました。
ゴドゥノフ朝の崩壊と、まさかの皇帝即位
偽ドミトリーの軍隊は、当初はロシアの正規軍に比べて数も装備も劣っており、いくつかの戦闘では敗北も経験しました。しかし、彼にとって最大の武器は、武力ではなく「自分こそが正統なツァーリ、ドミトリー皇子である」という主張そのものでした。
「本物の皇子が生きていたらしい!」という噂は、大飢饉と圧政に苦しみ、ボリス・ゴドゥノフ政権に不満を抱いていたロシアの民衆や、自由を求めるコサックたちの間に急速に広まり、彼らの希望の星となっていきました。ロシア南部の諸都市が次々と偽ドミトリーに味方し、彼の軍勢は進むにつれて雪だるま式に膨れ上がっていったのです。
そんな中、偽ドミトリーにとって決定的な幸運が訪れます。1605年の4月、敵であるはずのツァーリ、ボリス・ゴドゥノフが、原因不明の病で急死してしまったのです。後を継いだのは、まだ16歳の若き息子、フョードル2世でした。しかし、父のような政治力もカリスマも持たない若い皇帝に、この国難を乗り切る力はありませんでした。ゴドゥノフ政権は急速に統制を失い、内部崩壊を始めます。
ゴドゥノフ側の軍隊を率いていた将軍たちの中からも、偽ドミトリー側へ寝返る者が続出しました。そしてついに、首都モスクワを守るべき大貴族たちまでもが、偽ドミトリー支持へと舵を切ります。1605年6月、モスクワ市内でクーデターが発生し、哀れな若き皇帝フョードル2世とその母(ボリス・ゴドゥノフの妻)マリヤは、裏切り者たちの手によって無残にも殺害されてしまいました。
こうして、偽ドミトリーがロシアの首都モスクワへ入城するための道は、完全に開かれました。
1605年6月20日(ユリウス暦)、偽ドミトリーは、彼を「救世主」「正統なツァーリ」と信じるモスクワ市民たちの熱狂的な大歓声に迎えられながら、堂々と首都に入城しました。彼はさらに自らの正統性を演出するため、かつてウグリチで死んだとされる本物のドミトリー皇子の実の母親、マリヤ・ナガヤ(彼女はこの時、マルファという名の修道女となっていました)を、長年追いやられていた修道院からモスクワに呼び寄せます。そして、クレムリン宮殿の前で、大勢の群衆が見守る中、マリヤ(マルファ)は偽ドミトリーを指さし、「おお、我が息子、ドミトリーよ!」と叫び、涙ながらに彼と抱き合ったのです。
これが真実の母子の再会だったのか、それともマリヤが政治的な圧力や計算から偽ドミトリーを息子だと認めるしかなかったのか、その真相は歴史の闇の中です。しかし、この「母との感動の再会」劇は絶大な効果を発揮し、偽ドミトリーの正統性を疑う声は(少なくとも表向きは)封じ込められました。
そしてついに、偽ドミトリー1世は、全ロシアのツァーリとして正式に戴冠しました。死んだはずの皇子が、奇跡の生還を果たし、父(イヴァン雷帝)の玉座に就いた… まさに、信じられないような物語が現実となった瞬間でした。
皇帝の座も束の間:疑惑と反感
ツァーリとしてロシアの頂点に立った偽ドミトリー1世。彼は若く(おそらく20代半ば)、エネルギッシュで、ポーランドで西欧的な文化や知識にも触れていたため、当初はその統治に期待する声もありました。彼は、自分を支持してくれた貴族たちに領地や官職を与え、一時的に農民の税負担を軽減するなど、人心掌握にも努めました。
しかし、彼の振る舞いや政策は、次第に、伝統とロシア正教を重んじる保守的なロシアの貴族、聖職者、そして一般民衆の間に、強い疑念と反感、そして失望感を生んでいくことになります。
異質な文化と習慣
彼は、ロシア古来の伝統的な儀式や宮廷の作法を軽視し、ポーランド風の華やかな服装や、西欧的なマナーを好んで取り入れました。これは、多くのロシア人にとって異質で、不快なものに映りました。
宗教的な問題
彼はロシア正教会の伝統や権威を尊重する姿勢を見せず、むしろカトリック教会に好意的な態度を示しました(彼自身が秘密裏にカトリックに改宗していたことが、後に大きな問題となります)。これは、敬虔な正教徒である多くのロシア人にとって、到底受け入れられるものではありませんでした。
外国人びいき
彼は、自分を支援してくれたポーランド人や、その他の外国人(ドイツ人など)を側近として重用し、彼らに重要な役職や特権を与えました。一方で、ロシアの伝統的な大貴族(ボヤーレ)たちは、政治の中枢から遠ざけられる傾向にありました。
ポーランドとの関係
彼がポーランド側に約束していたロシア領土の割譲などは実行しませんでしたが(できなかった、とも言えます)、ポーランドとの友好関係を維持しようと腐心する姿勢は明らかであり、「ポーランドの傀儡ではないか?」という疑念を招きました。
マリーナ・ムニシェクとの結婚
決定的にロシア人の反感を煽ったのが、1606年5月に行われた、ポーランド貴族の娘マリーナ・ムニシェクとの結婚式でした。マリーナは、ロシアの皇后となるにも関わらず、カトリック信仰を捨ててロシア正教に改宗することを頑なに拒否しました。さらに、彼女と共に花嫁行列としてモスクワにやって来た数千人ものポーランド人の随員(貴族や兵士)たちの、横柄で傲慢な振る舞いは、モスクワ市民の怒りを買いました。結婚式自体も、ロシアの伝統を無視したカトリック風の要素が取り入れられ、その後の数日間にわたる豪華絢爛な祝宴も、飢饉の記憶が生々しい民衆にとっては、贅沢で不謹慎なものと映ったのです。
反乱と無残な最期

偽ドミトリー1世に対する不満と怒りは、もはや限界点に達していました。そして、その状況を巧みに利用し、反乱の機運を煽ったのが、有力な大貴族であり、かつてドミトリー皇子の死因調査を指揮した経験を持つ、ヴァシーリー・シュイスキーでした。
シュイスキーは、かつては偽ドミトリーの正統性を認める側に回ったこともありましたが、今度は手のひらを返し、「今のツァーリは、本物のドミトリー皇子ではなく、悪魔に唆された逃亡修道士グリゴリー・オトレピエフという名の偽物に違いない!」「彼はロシアをポーランドに売り渡そうとしている異端者だ!」と声高に叫び、他の不満を持つ貴族や聖職者、そしてモスクワ市民を扇動し、偽ドミトリー打倒の陰謀を着々と進めていきました。
そして、マリーナとの結婚式からわずか9日後の1606年5月17日(ユリウス暦)の早朝、ついに反乱の火ぶたが切られました。シュイスキーらに率いられた武装した貴族、兵士、そして興奮したモスクワ市民たちが、「偽ツァーリを殺せ!」「ポーランド人を叩き出せ!」と鬨(とき)の声を上げながら、クレムリン(皇帝宮殿)へと殺到したのです。
完全に不意を突かれた偽ドミトリー1世は、わずかな側近と共に宮殿の窓から飛び降りて逃亡を図りますが、すぐに反乱軍に発見され、捕らえられてしまいます。彼は必死に自分が本物のドミトリー皇子であると訴えましたが、もはや誰も彼の言葉に耳を貸しませんでした。彼はその場で、弁明の機会も裁判もなく、槍やサーベルで滅多突きにされ、銃で撃たれて、無残にも殺害されてしまいました。皇帝としてロシアを統治した期間は、わずか11ヶ月ほどでした。
反乱軍の怒りは死してなお収まらず、偽ドミトリー1世の遺体は衣服を剥ぎ取られ、道化師の仮面をかぶせられて、モスクワ市中を引きずり回され、赤の広場で見せしめにされました。その後、遺体は焼かれ、さらにその遺灰は、彼が忌まわしい異端と外国の影響をもたらした象徴として、大砲に詰められ、彼がやってきた西の方角、すなわちポーランドの方向に向けて発射された、という凄惨な伝説まで残されています。
このクーデターでは、彼の妻となったばかりのマリーナ・ムニシェクは、かろうじて殺害を免れましたが(彼女は後に、別の偽ドミトリー2世と結ばれるなど、さらに波乱の人生を送ります)、彼女と共にモスクワに来ていた多くのポーランド人の随員たちも、怒り狂った市民たちの手によって虐殺されたり、捕虜となったりしました。
まとめ:動乱ロシアが生んだ「なりすまし皇帝」
偽ドミトリー1世。彼の短いながらも劇的な生涯は、17世紀初頭のロシアを襲った大混乱期、「動乱時代(スムータ)」がいかに異常で、予測不可能な時代であったかを、私たちに鮮烈に物語っています。
正統な王朝が途絶え、社会が不安定になり、人々が救世主の登場を渇望する中で、「死んだはずの皇子」という、まるで物語のような存在への期待感が、一介の(おそらくは)修道士を、信じられないことに本物の皇帝の座にまで押し上げてしまいました。そして、その状況を自国の利益のために利用しようとした隣国ポーランドや、ロシア国内の様々な勢力の思惑が複雑に絡み合い、事態はさらに混迷を深めていったのです。
しかし、彼がいかに巧みに「本物のドミトリー皇子」を演じきったとしても、その出自の怪しさと、ロシアの伝統や民衆感情を無視した振る舞いは、最終的に彼の命取りとなりました。彼は、自らが利用したはずの民衆の熱狂と、貴族たちの野心によって、わずか1年足らずで打ち倒され、歴史上最も有名な「なりすまし皇帝」として、その名を残すことになったのです。
彼の死後も、「我こそはドミトリー」と名乗る第二、第三の偽ドミトリーが現れ、ロシアの動乱はさらに十数年も続くことになります。偽ドミトリー1世の物語は、歴史の大きな転換期や混乱期には、時に信じられないような「偽り」がまかり通り、そしてそれが悲劇的な結末を迎えることがあるという、一つの普遍的な教訓を私たちに示しているのかもしれません。
※本記事では英語版も参考にしました








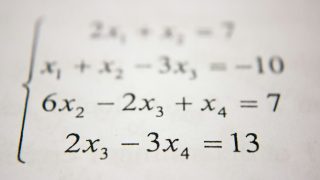














コメント